本間忠良の「技術と競争ワークショップ」はhttp://www.tadhomma.sakura.ne.jp/へ移動しました。これからもよろしく。
![]() 本間忠良 衝撃の新刊 知的財産権と独占禁止法−−反独占の思想と戦略
本間忠良 衝撃の新刊 知的財産権と独占禁止法−−反独占の思想と戦略
経済法あてはめ演習60選(日本語)Antimonopoly
Act Exercise 60 Cases![]()
情報革命についてのエッセイとゴシップ(日本語) Essays and News on Information Revolution![]()
松下教授還暦記念論文集『企業行動と法』(商事法務研究会、1995年3月)
目次
はじめに
1.略奪論
1.1.略奪価格モデル
1.2.略奪価格設定は(なぜ)悪いか
1.3.アリーダ・ターナーとその発展
1.4.シカゴ学派
2.松下判決
2.1.背景
2.2.提訴
2.3.地裁略式判決 513 F. Supp. 1100 (E.D.Pa., March
27, 1981)
2.4.高裁(第3巡回裁)判決 723 F.2d 238 (3rd Cir.,
December 5, 1983)
2.5.最高裁判決 475 U.S. 574, 89 L Ed 2d 538, 106 S.Ct.
1348 (March 26, 1986)
2.6.高裁(第3巡回裁)再判決 807 F. 2d 44 (3rd Cir.,
December 12, 1986)
3.松下からブラウン&ウイリアムソンまで
3.1.松下判決の評価
3.2.ブラウン&ウイリアムソン(B&W)判決
4.さいごに
注
参照文献(著者名アルファベット順)
1987年に結審したいわゆる米国最高裁松下事件判決を、いまここで再論する理由はすくなくとも3つある。第1は、現在、何度目かの「流通革命」を通過中の日本で、安売りとはなにか、競争とはなにか・・という根源的な疑問が提起されており、松下判決がそれに対する有力な答えを用意していること、第2は、クリントン政権の通商政策決定過程に大きな影響力を持ついわゆる「戦略貿易政策論」が、その出発点の一つとして、松下判決で決着したはずの日本のテレビ通商政策をとりあげていること、第3は、最近のブルックス対ブラウン&ウイリアムソン米国最高裁判決が、松下判決とひとつながりの判決と目されることである。
本稿では、第1部で略奪についての基本概念を整理し、第2部で松下事件の背景と判決について、第3部で松下判決後の学説・判決の動向について述べる。松下判決は、単なる略奪価格設定事件というよりはるかに広い問題をカバーしているのだが、略奪以外の問題については巻末注に譲った。引用文献については巻末文献リストを参照されたい。
略奪(predation )およびその主要な形態である略奪価格設定(predatory pricing)に関する議論は、経済法文献の中でかなりのページを占めてきた。松下からブラウン&ウイリアムソンにつながる最高裁の思想と比較するため、以下に、略奪論の流れを簡潔に回顧してみよう。
ここでは、略奪を、「生産者が、短期的利潤を犠牲にして市場占有率を拡大し、よって長期的利潤を増大させること」と定義し、略奪価格設定を、「生産者が、まず原価割れ販売によって競争者を排除ないし牽制し、次に価格を吊り上げて超過利潤を獲得すること」と定義する(Brodley & Hay, p.741参照)。また、もっぱら略奪価格設定を論じ、非価格略奪については必要に応じて触れる程度にする。
ミクロ経済学の文献でよく使われる第1図(縦軸pが金額、横軸qが数量)のアイデアは、実際にも、生産者の短期事業計画で使われている。生産者は、新製品発売に先だって、まず、市場調査によって、価格をいくらにすればどのくらい売れるかを予測し、需要曲線DDを得る。テレビのような不完全代替財の需要曲線は右下がりの曲線になるのがふつうである。需要曲線の傾きや曲率は市場によって与えられるので、短期的には生産者サイドで左右できるものではない。
他方、総費用(固定費用+変動費用)は、一般に、収穫逓減の法則にしたがって、総産出量が大きくなるにつれて、はじめは急速に、ついで緩慢に、最後にふたたび急速に増加し、収穫の限界に達する(Hirshleifer, p. 267)。一定の産出量に対応する総費用をその産出量で割ったものが平均費用である。平均費用曲線ACは、産出量が大きくなるにつれて下降し、最小点に達してからふたたび上昇するので、上から見て凹型になる。平均変動費用曲線AVCは、平均費用曲線をその産出量に対応する平均固定費用の分だけ下方に移動したものである。
つぎに、限界費用とは、産出量を一単位増やしたときの総費用の増加分である。限界費用曲線MCも上から見て凹型になる。限界費用曲線は、まず、平均変動費用曲線を、ついで平均費用曲線を、それぞれの最小点で下から切る。
総費用曲線は生産者サイドである程度決定でき、それにともなって限界費用曲線と平均費用曲線が決まる。需要曲線と限界費用曲線の交点に対応する価格poと産出量qoで、社会的な需要と供給が一致する(均衡点A)。
第1図
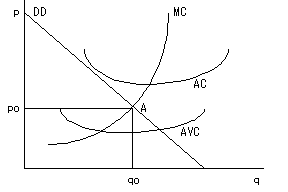
この設問に対してはいろいろな説明がなされているが、かつての、「売手が、自分のビジネスのほんの一部を犠牲にして、一定地域に閉じこめられている中小競争者の全ビジネスを脅かす」(Areeda & Turner 1978, v. 3, p. 186)ことを不正義とした中小企業保護イデオロギーにもとづく説明は影響力を弱め、かわって、「それが社会的な効率損失をもたらすから」というドライな説明が、現在では有力になっている。
略奪価格設定は、かならず、1)原価割れによる安値販売(投資局面)と、2)それが成功した場合の独占による高値販売(回収局面)という二つの局面からなる。
投資局面(第2図)において、略奪者は、意図的に限界費用より安い価格をつけ、均衡点Aより低い価格pp、大きい産出量qpに対応する投資点Cに移行する。ここでは、生産者が損失を受けるが、その分消費者の利益になる(transfer)ので、これだけで見れば、社会的には差引きゼロである。しかし、社会は、図形ABCと図形ACDであらわされる社会効率損失(deadweight loss)をこうむる。つまり、もともと社会が必要としていなかった製品の生産や消費のために投入された資源や金が、他のもっと必要な製品の生産や消費から剥奪されているのである。
第2図
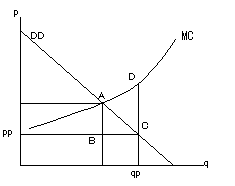
つぎに、原価割れ販売という略奪投資によって競争者の排除ないし牽制に成功し、独占的地位を確立した略奪者は、価格吊り上げに転じて、いよいよ、いままでの投資を回収する局面に入る。回収局面(第3図)において、略奪者は産出量をqpからqmまで減らし、価格をppからpmまで吊り上げる。
ここで、限界収入とは、産出量を一単位増やしたときの総収入の増加分である。数量を増やすと価格が下がるので、限界収入曲線MRは需要曲線より傾きの大きな右下がり曲線になる。限界収入曲線と限界費用曲線の交点で利潤が最大になるため、独占生産者はこの点に対応する価格pm(poより高い)と産出量qm(qoより小さい)を選択する。つまり、独占生産者は、需要と供給が過不足なく一致する社会的均衡点Aではなくて、利潤最大化点Cを選択するのである。
ここでは、生産者が利益を受けるが、その分消費者の損失になる(transfer)ので、これだけで見れば、社会的には差引きゼロである。しかし社会は、図形ABCと図形ABDであらわされる社会効率損失(deadweight loss)をこうむる。つまり、価格poなら買われたはずの製品が買われなかったり、価格poなら生産されたはずの製品が生産されなかったことによって生じる社会的損失である。
要するに、略奪の過程で、無駄な投資と無駄な貯蓄が発生するのである。すくなくとも、投資と回収のふたつの局面で生じるこれらの社会効率上の損失が、略奪価格設定を違法とする経済的根拠である。
第3図
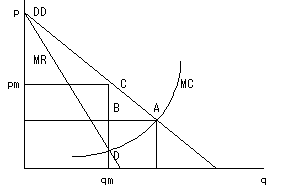
略奪が成功するためには、1)投資局面では原価割れ販売による競争者排除ないし牽制が、また、2)回収局面では高い参入障壁に守られた独占、買収またはカルテルによる価格吊り上げが、3)また両局面が同時に異なる市場でおこなわれる場合は価格差別が必要で、これらの行為がそれぞれ反トラスト諸法と接触する。
略奪価格のわかりやすい推定基準を作ろうとする学界の努力は、まず、1975年、アリーダとターナーによる記念碑的論文(Areeda & Turner 1975)に始まる。アリーダ・ターナー論文は、投資(安売り)局面において、限界費用未満の価格設定に経済的合理性が認められないことを根拠として、これをシャーマン法2条(独占行為)またはロビンソン・パットマン法(価格差別)違反とする(Areeda & Turner, p. 725)。ただし、一般の企業では限界費用管理をおこなっていないから、限界費用を平均変動費用で近似し、1)合理的に期待できる短期的平均変動費用以上の価格を合法、2)それ未満の価格を違法と推定することを提案する(Id. p. 733)。
シャーラーは、略奪者が、あらかじめ、利潤最大化点より大きい産出量・安い価格(ただし限界費用以上)を設定し、自分と同程度に能率的な新規参入者を阻止する戦略をとる可能性があることを示し、アリーダ・ターナー・テストのような簡便法ではなくて、あらゆる事実を勘案した合理の原則で判断することを提案する。
ジョスコウとクレヴォリックは、略奪価格設定が独占市場でしか利潤を生じない点に着目し、1)まず関連製品市場における独占状態の存在を認定し、2)ついで平均変動費用と操業度、それに安売りから2年以内における価格吊り上げの有無を基準として、略奪価格設定行為の存在を認定するという2段階法を提案する。
ウイリアムソンは、略奪者が、あらかじめ、利潤最大化点より大きい産出能力を保持しておいて、新規参入があった場合、自分の産出量を増加しかつ短期的平均費用を低下させることによって、参入者を平均費用割れに追い込みつつ、自分は限界費用以上にとどまる戦略をとる可能性のあることを示し、新規参入開始後18か月間、略奪者(インサイダー)の産出量増加を禁止するというルールを提案する。
バウモルは、なんらかの費用を基準とするテストでは、価格メカニズムによる資源配分の効率性確保ができないとしてこれに反対し、かわりに、略奪の回収局面に着目して、安売りによって競争者を排除ないし牽制した支配的生産者に対して、一定期間値上げを禁止するというルールを提案する(以上、Brodley & Hay, p. 755ff/McGee 1980, p. 306ff)。
ポズナーは、平均費用未満の販売と略奪的意図があれば略奪が成立するというテストを提案する(Posner, p. 189ff)。
アリーダ・ターナー論文は、実用的な平均変動費用を境界値として使うことによって、競争促進的な安売りに対する競争者からの濫訴を抑制しようというねらいを持っていたらしいのだが、実際には、逆に、70年代後半から80年代前半にいたる略奪価格訴訟のラッシュを誘発したといわれる。リーベラーは、75年までの30年間きわめてまれだったシャーマン法2条違反の略奪価格設定判決が、それ以後の10年間には55件に達したことを報告している(Liebeler, p.1055ff)。
アリーダ・ターナー以下の、なんらかの費用を基準にして合法・違法の線を引いたり、産出量増加や値上げを禁止するという規制型の諸提案に対して、いわゆるシカゴ学派の学者グループから、このようなアプローチがかえって企業間の真の競争を阻害し、資源の効率的利用を妨げ、ひいては消費者福利を害するという批判が加えられている。
マッギーは、先駆的な1958年論文で、1911年のスタンダード石油最高裁判決(シャーマン法2条違反)を再検討した結果、被告が略奪ではなく、利潤最大化動機によって行動していたことを示し(McGee 1958, p. 168 )、また、同テーマの再論で、ウイリアムソン等の規制型提案を「ますます複雑珍奇な戦略行動モデルの洪水」だとして、痛烈に批判する(McGee 1980, p.315 )。
ボークは、「競争とは、本来、競争者がお互いを排除しようとする過程に他ならない」(Bork, p. 49)という観点から、「(シャーラー以下が示したような戦略的)テクニックによる略奪は極めてまれだから・・そのような存在しない可能性のある行為を抑止するためのルールを作るのは・・むしろ有害ですらある」という(Id. p. 154)。
イースターブルックは、「略奪者が直面するリスクと競争者の反撃を考えた場合、一見もっともらしいこれらの戦略が、略奪者にとって利益になる可能性はすくない」から、「反トラスト法が略奪を本気で心配する理由がない」(Easterbrook, p. 264)として、「反トラスト法に当然合法(per se legal)ルールを設ける余地があるのなら、そこには略奪行為が入るべきだ」とまでいう(Id. p. 337)。
エルジンガは、シカゴ学派が到達した略奪非実在論を、現在クリントン政権が採用しつつあるタイソンたちのいわゆる戦略貿易政策論に対する批判にまで拡大する。戦略貿易政策論とは、要するに、現実の世界市場が不完全競争状態にあるゆえに生じるレント(略奪による超過利潤)の争奪をめぐって、国家による貿易政策の存在理由があるというものだが(Krugman,
p. 14/25/29/32/73 )、エルジンガは、そのような政策が、反トラストの世界において略奪実在論者が抱いたのと同じ妄想にもとづくものであり、結局は米国消費者の福利に反することになると警告する(Elzinga,
p. 966)(注1)。
1957年にブームをむかえた日本のモノクローム・テレビ市場は、1960年代はじめ普及率が飽和点に達し、その後次第にオール・トランジスター卓上型へ移行、70年代に入って急速に衰退した。カラーテレビの生産は1964年から統計にあらわれはじめ、年々倍増して67年には金額ベースでモノクロームを抜いた。
1960年ごろ、米国は普及率で日本を5年以上リードしていたが、1960年代後半、メーカーがオール・トランジスター型への切替えを怠り、その空隙を満たすべく日本製テレビの対米輸出が急増した。日本におけるテレビのオール・トランジスター化、そしてオールIC化は、75年以後、部品の自動挿入、さらには全自動組立てを可能にし、米国メーカーとの生産性格差を決定的なものにした。これ以後、日本では、民生電子商品と半導体というふたつの産業の間にプラスのフィードバック過程が進行する。
このころの日本の家電流通機構には一本のハッキリした変化の方向がみられる。
1950年代なかごろ、家電メーカーは倍額増資をくりかえして設備を増強し、巨大な供給能力を持つに至った。他方、消費者のほうも、いわゆる三種の神器(洗濯機、テレビ、冷蔵庫)に対する強い需要を持っていた。
問題は巨大な生産と巨大な消費のあいだをつなぐ流通のパイプが細いことだった。メーカーが大量の製品を資金難の卸業者に「押し込み」、卸業者はこれを2、3次卸までまわして資金を工面しつつ、零細な小売店に押し込む。各段階での代金決済はほとんどが手形である。そのころ、消費者はちょうど月賦の味をおぼえたばかりのところで、小売店は自己資金による月賦販売の誘惑に負け、当然資金繰りにつまって、在庫品を仕入れ原価割れで金融筋に持ちこむ(バッタ取引き)。流通業者が連鎖倒産していく一方、バッタ品が市場に出まわって値崩れをおこし、さらに流通業者を圧迫するという悪循環が当時あった。 このボトルネックを打開するため、メーカーは、1)1次卸を子会社化、2)2、3次卸を回避(巨大小売店に転業したものが多い)、3)小売店を各種リベートと非価格補助で協力店化、4)そして月賦販売資金をメーカー直営の月販会社が肩代わりという政策を遂行してきた。これが販売網の系列化と呼ばれる産業現象である。
この間の1957年、メーカーの組織「市場安定協議会」が、そのいわゆる市場安定綱領9項目の破棄をもとめる公正取引委員会の勧告を応諾、さらに1966年、公取委が、テレビ・メーカー6社(ソニー除く)に対し、価格協定容疑で審判を開始、審決案まで行ったが、これは77年打切り処分となった。
ブランド間競争は激烈で、70年には、小売り表示価格と実売価格の乖離が平均20%を超えるというような事態になった(70年公取委調べ)。さらに、カラーテレビの国内小売り表示価格と米国大口購買者(シアーズなど)むけの輸出卸実勢価格を二重価格だと誤解したマスコミ報道が流れた。これらの事態がダンピングの特徴である1)内外価格差、2)需要の価格弾力性の低さ、3)外国品に対する参入障壁(注2)として、米国人の目に映ったのである(注3)。
他方、1960年代はじめ、日本製(モノクローム)テレビの対米輸出開始に早くも脅威を感じた米国メーカーからの通商圧力が強まったため、通産省は、トランジスタ・ラジオの経験にならって、テレビ業界に対して、対米テレビに関するいわゆるチェックプライス協定を締結するよう指示、1963年、輸出入取引法にもとづくメーカー協定と輸出組合規約がそれぞれ成立、以後、多少の曲折はあっても、両協定は毎年更新され、73年、おなじく通産省指示により廃止されるまで、10年にわたって存続した。
1968年、米国電機工業会(EIA)は、1921年反ダンピング法にもとづいて日本製テレビを提訴、これが史上最大のダンピング事件に発展した。70年当時担当官庁だった財務省(80年以後は商務省)がLTFV(公正価額割れ)クロ決定、71年関税委員会(74年以後は国際貿易委員会)が被害クロ決定、これによってダンピング決定告示、関税評価が差止められた。以来、財務省からは1年目の反ダンピング関税として全メーカー分として約百万ドルと査定してきたほか、ハッキリしたアクションがなく、立入り調査(verification)にも来ないまま、「物品税方式」爆弾が落ちるまで7年間、関税評価が差止められた状態で輸出量だけが増大していった。想像するに、財務省は、関税評価差止めだけで十分輸入抑制効果があると思っていたのが、議会保護主義勢力の圧力に耐えきれず、ついに「物品税方式」に及んだというのが真相であろうか。
78年、財務省は、輸入者側の情報提供が不十分だとして、みなし課税(best information available)方式を採用、日本の物品税対象価額をFMV(外国市場価額)とみなすむね通告してきた。当時テレビの物品税は倉出し価格(税引き)の15%だったが、倉出し価格の計算は面倒だから、そのかわりに、テレビの場合、小売り表示価格の62%を倉出し価格とみなしていいことになっていた。これで計算した場合、全期間で4億ドルという巨額の反ダンピング関税になるため業界は大騒ぎになった。輸入業者は直ちに異議申立て、日本政府もくりかえし抗議をおこなった。
こうしているうちに、あたらしいGATT反ダンピング・コードを受容する1979年通商協定法が発効、担当官庁として財務省から代わった商務省が輸入業者と個別のネゴにはいり、80年、過去分総額 7,600万ドルで示談成立。米国保護主義団体はこの示談を不満として国際貿易裁判所(CIT)に提訴、示談停止の仮処分まで行ったが、最終的には有効判決があり、過去分は解決。これ以後の分は通常の手続きにより現在も係属中。
物品税については、また別の問題があった。70年、ゼニス社は、日本の物品税の輸出免税が輸出補助金にあたるとして、相殺関税法にもとづく提訴をおこなったのである。76年財務省シロ決定あるも、これが関税裁判所(いまのCIT)で逆転クロ、関税特許控訴裁(いまのCAFC)で再逆転シロ、83年最高裁がこれを支持して一件落着。
70年12月、米国の家電コングロマリットNUE(National Union Electric )が、日本のテレビ・メーカー7社(日立、東芝、三菱、松下、三洋、シャープ、ソニー)およびそれらの国内輸出商社ならびに現地販売会社(三菱商事および米国三菱商事を除き、いずれもメーカー子会社)を、シャーマン法1条、2条、ロビンソン・パットマン法2条a、ウイルソン関税法73条および1916年反ダンピング法違反の容疑で、ニュージャージー連邦地裁に提訴した。のち、74年9月、米国第2のテレビ・メーカー、ゼニス社が、同様の訴因でペンシルヴァニア東部連邦地裁に提訴、同年両事件は後者に併合された。(後者は訴因にクレイトン法7条を追加、また、被告にモトローラ、シアーズ等を加え、かつ製品範囲をトランジスタ・ラジオ、テープレコーダー、ステレオ、電子部品にまで拡大しているが、本稿では訴因をシャーマン法にしぼり、被告を前記7社、製品をテレビにしぼって述べる)。請求は3倍賠償にして18億ドル以上。
原告側の主張は複雑かつ二転三転したが、結局、原告側最終弁論書によると、「被告は、『単一の共謀』によって、日本国内向けテレビの価格を人為的な高水準に固定維持すると同時に、対米テレビの価格を人為的な低水準に固定維持し、原告を米国市場から駆逐しようとした」というものであり、とくに、直接証拠として次の事実をあげている。
a)日本国内での価格吊り上げ共謀。1)1957年市場安定協議会勧告審決と、2)1966年テレビ6社に対する審判開始。
b)対米安値輸出共謀。1)いわゆるチェックプライス協定(対米テレビ各インチサイズごとの最低輸出価格を定めたもの・・メーカー協定と輸組規約とからなる)と、2)いわゆる5社枠(米国内取引先を登録させたもの・・輸組規約)。
c)対米ダンピング。70年財務省、71年関税委員会による1921年反ダンピング法にもとずくクロ決定。
原告側の戦術としてここで特筆すべきことは、原告側が、上の断片的な事実そのものをシャーマン法違反だとしているのではなく、これらがいわゆるprima facie evidenceとなって、前述「単一の共謀」の存在が推定されるとしている点である(「共謀事件では直接証拠をとるのが困難なので、状況証拠による推定が重要な役割をはたす」本件高裁判決 723 F. 2d 238, 83a)。
76年から79年にかけておこなわれた事実問題に関する証拠調べ(discovery)では、日本被告側から提出された文書数百万枚、証言録取(deposition)十数人、尋問書(interrogatories)数百項目という、米国独禁訴訟史上まれに見る大規模訴訟に発展した。
79年全被告によって提出された1)1916年反ダンピング法適用と、2)シャーマン法違法推定に関するふたつの略式判決申立てが、80年と81年それぞれ連邦地裁でみとめられ、事実上被告側の勝訴となった。ダンピングについては注記に譲り、ここではシャーマン法違反推定に関する略式判決についてのみ述べる。
まず、連邦民事訴訟規則56条は、原被告いずれも、訴因の全部または一部について、公判(trial)を待たずして略式判決(summary judgment)を求めることができると規定している。同条によると、1)まず、申立人が「重要な事実に関する真の争点」(genuine issue for material fact )の不存在を立証することが必要で、この立証が成功したら、2)被申立人は、自己の訴状や答弁書の主張を繰返したり、申立人の主張を否認するばかりではダメで、公判にあたいする真の争点の存在を示す事実を特定しなければならない。
略式判決申立てに先だって、日本被告側は、原告側最終弁論書に添付の証拠および鑑定人意見書の採否に関するヒアリングを要求、80年9月、判事はこれらのほとんどについて不採用の決定を下した(注4)。判事は、続いて、不採用をまぬがれたわずかな証拠では、重要な事実に関する真の争点の不存在という被告側の立証に対抗できないとして、全訴因に関し被告側有利の略式判決を下した。判事は、原告の主張が、日米両国における被告の平行的行動から帰納される推定にすぎないと判断、かかる推定が次の二つの理由によって失当であると判示した。
a)被告側共謀を示唆する若干の直接証拠はある(チェックプライス協定と5社枠)が、これは原告に被害を与える性格のものではない(高値販売協定だから、競争者である原告に被害が発生するはずはない)。
b)米国内での安売り共謀に関連して提出された証拠は、被告各社の行動が、独占企図ではなく、正常な競争行動だったという、より説得力ある推定を覆すに足りるものではない。これがいわゆるシティズ・サービス原則である(注5)。(いわゆるリベート問題については注6を参照されたい)。
c)シャーマン法1条違反不成立のゆえに、シャーマン法2条違反も不成立。
83年12月、第3巡回裁は、地裁の上記両略式判決を破棄差戻した。高裁は、地裁が不採用とした証拠および鑑定人意見書の大部分を復活させた。地裁は証拠や鑑定人意見書の採否について裁判官の裁量権をフルに行使したのであるが、高裁は、とくに鑑定人の能力の判断は陪審員の任務だと考えたのである。この結果、本件について、高裁は、「日本における価格協定の直接証拠が、より広い共謀の状況証拠として使える可能性あり」(723 F. 2d 238, 165a) 、これら直接間接の証拠を総合的に見た場合、陪審員が「日本国内での超過利潤に支えられ、米国の競争者を駆逐するため米国で安売りする共謀」(Id. 175a) を発見する可能性あり、したがって略式判決は誤りだったと判断した。
本最高裁判決は、略奪価格設定行為の推定基準として、経済的動機の有無を採用したという点で画期的な判決となった。判決は5対4の僅差であった。意見書はパウエル判事によって書かれ、バーガー長官、マーシャル、レーンキスト、オコナーの各判事が同調、反対意見はホワイト判事によって書かれ、ブレナン、ブラックマン、スティヴンズの各判事が同調した。
a)被害との因果関係。判決は、まず、「原告は、日本国内市場でのカルテル容疑のみを根拠として、反トラスト損害を回収することはできない」(106 S. Ct. 1348, 549 )と前提する。
b)立証責任。最高裁は、さらに、かかる略奪価格設定の訴えを維持するに必要な証拠のレベルについて、「もし、事実に関する文脈が、原告の請求を経済的に不合理なものに陥れる場合は、原告の立証責任が加重されるべきだ」(Id. 552)という。
c)略奪価格設定。最高裁は、本件における原告の請求が経済的に不合理であると結論する前提として、略奪価格設定行為について次のような観察をおこなった。「そもそも、略奪価格設定共謀は、その本質上、投機の性格を持つ。略奪価格として競争水準より低い価格をつける共謀は、共謀者が自由競争下より低い利潤しか得られないことを意味する。この失われた利潤は将来への投資と考えられる。かかる投資が正気なものであるためには、後日の独占利潤によって、失われた利潤(を複利増価したもの)以上のものを回収できるという合理的な期待がなければならない。・・略奪価格設定においては、短期的損失は確実だが、長期的利益は不確実である。そればかりでなく、回収段階では、独占だけでは不十分である。なぜなら、独占による高価格は新規参入者をひきよせるからだ」(Id. 553-4)。最高裁は、略奪価格設定という行為そのものが、きわめて特殊な状況下を除いて、経済的に不合理な行為だと認識したのである。「問題とされている略奪共謀が20年かかっても成功していないという現実自体、かかる共謀が存在しなかったことの強力な証拠である」(Id. 556)。
d)結論。最高裁は事件を高裁に差戻した上、「再審理にあたっては、被告各社が、なんら明瞭な動機もないのに、20年にもわたって略奪価格設定共謀をおこなったと陪審員が納得し得る十分に明白な証拠が、『他に』あるかどうか審理してもいい。しかし、そのような証拠は、被告各社が、競争に応えるために値下げしたのだという可能性を排除する傾向を有するものでなければならない」と判示した(Id. 559)。これがいわゆるモンサント原則である(注7)。
e)反対意見。本判決における反対意見の大要は次のようである。「本判決は、陪審の領域を侵害するいくつかの判断をおこなっている。判決は、『高裁が、被告の安売り行為が独立のものであって、共謀ではなかった可能性について考えなかった』と言っているが、これは、伝統的な略式判決の基準を超えて、証拠の優越をみずから判断したものである。ディポドウィン報告書(注4)だけでも『真の事実問題』を構成する」。
a)判決。第3巡回裁は、「最高裁の判断を覆すためには、(最高裁が審理した)以外の証拠が必要なのだが、原告は、『最高裁の判断が誤っている』と主張するだけで、新しい証拠を全く提出していない。したがって、全訴因に関し、一審地裁の略式判決を支持する」と判決。
b)被告側勝訴確定。87年4月24日、原告からの事件移送申立てを最高裁が却下、かくて被告側勝訴が確定した。
1916年法ダンピング問題と政府強制問題については、それぞれ注8、9を参照されたい。
81年以来最近までの法律文献データベースを「ゼニス対松下事件」をキーワードとして検索して得られた25件の雑誌論文を通読して、全体の傾向を観察した。一般に、松下判決肯定論に充実したものが多く、すべていわゆるシカゴ派の競争観に立っているといってよい(文末文献リスト◎印)。これに対して、否定論(同●印)は、1)略式判決が不適切だった(被告側原価割れのディポドウィン証言に証拠能力を認める具体論と、陪審の権利を重視する一般論とに分かれる)という法律論と、2)長期的または文化的観点から見て、被告側に略奪の動機があり得たという経済論の2種類に分かれる。後者のなかには、典型的な日本異質論が含まれる(Crew/Benz)。ほかに、中立論(同○印)のなかにも、いろいろな略奪動機に関する考察が見られるが、概していえば、いずれにおいても、マッギーによる「ますます珍奇複雑な戦略行動モデルの洪水」(前述)という批判に耐えられるものはすくない。
松下判決以後の下級裁における略奪判決を分析したオースチン(Austin)によると、松下判決はシャーマン法1条事件だから、同2条やロビンソン・パットマン事件には適用しないときわめて狭く限定した1例 Marsann v. Brammall, 788 F. 2d 611 (9th Cir. 1986) を除いて、一般の下級裁は松下判決を広く解釈しており、とくに、当然ながら、 イースターブルック判事の A. A. Poultry Farms v. Rose Acre Farms, 881 F. 2d 1396 (7th Cir. 1989) は、シャーマン法2条、ロビンソン・パットマン法いずれにおいても、市場構造が回収を不可能にしている場合は、かりに原価割れと意図が存在しても、法律問題として判断する(略式判決が相当)としている由である。また、シムコビック(Simkovic)によると、下級裁の略奪事件では、経済的動機だけでなく、原告請求に対するフィルターや立証責任配分の根拠としてなんらかの費用を使ったり、意図を重視するなどの判決も依然健在である。さらに、ディサンティおよびコバシック(DeSanti & Kovacic)によると、連邦略奪事件における原告の勝率は、松下判決を境にして、27.6%(87件中24件)から34.4%(32件中11件)に上昇した由である。また、州法レベルでは中小企業保護タイプ(ダビデ対ゴリアテ図式)の略奪価格設定判決もまだまださかんなようである(たとえば最近のアーカンソー州裁 Wal-Mart 判決、BNA ATRR v.65, n.1636)。
米国のシガレット市場は長年安定した6社寡占だったが、80年、シェア最下位のリゲットが無印(むじるし)品に転換、ブランド品より30%低い小売り表示価格をつけ、かつ卸段階で量販リベートを展開するという価格政策を採用、依然最下位ながら、無印品でトップ、総合でもかなりのシェアを挽回した。しかるに、84年、業界3位、シェア12%のB&Wが無印市場に参入、卸段階で量販リベート競争をしかけ、リゲットを負かした。
リゲットは、B&Wが、量販リベートという競争阻害的価格差別によって、無印品の実売価格をその平均変動費用未満に設定、略奪価格設定をおこなったとして、ロビンソン・パットマン法違反で提訴、卸段階での量販リベート競争に生き残るため、小売り表示価格を上げざるをえなくなり、それが無印品市場の成長を妨げ、ブランド品市場におけるB&Wの超過利潤を確保することになったと主張した。
90年、115日におよぶトライアルの結果、地裁陪審はリゲットの主張を認め、B&Wに対する1.5 億ドル弱の損害賠償(3倍額)を評決したが、地裁判事は、競争阻害の欠如を理由としてこれを覆した(JNOV) Liggett Group v. Brown & Williamson Tobacco, 748 F. Supp. 344 (MDNC 1990)。92年、第4巡回裁は、「寡占者のひとりが、略奪価格設定行為からの損失を、寡占の特性を利用して回収しようとするのは経済的に不合理」として、地裁判決を確認した 964 F. 2d 335 (1992)。
93年6月21日、最高裁は6対3(レーンキスト長官、ケネディ、オコナー、スカリア、スーター、トマス各判事が賛成、ホワイト、ブラックマン、スティヴンスの各判事が反対・・この3人は松下判決でも反対意見)で、1967年のユタ・パイ判決Utah Pie v. Continenal Baking, 386 U.S. 685 (1967) 以来25年ぶりに、ロビンソン・パットマン法違反による直接競争者の被害を扱った判決を言い渡した。ケネディ判事が起草した意見書は、大要次のように言う U.S. S.Ct. No. 92-466 (BNA: Antitrust & Trade Regulation Report, v. 64, p. 802ff. 以下引用はATRRのページ番号)。
「ユタ・パイ判決以後の研究によって、ロビンソン・パットマン法違反の価格差別による直接競争者の被害は、シャーマン法2条違反の略奪価格設定行為による被害と同じ性質のものであることがわかってきた」(805) 。いずれにせよ、「反トラスト法は、競争者ではなく、競争の保護のために存在するものだから、原告は、自分が受けた被害ではなく、回収局面における、被告による「市場独占の危険なまでの蓋然性を立証しなければならない」(806) 。
一般に、原価割れ販売投資の回収(価格吊り上げ)のためには、独占かカルテルの存在が必要とされるのだが、これが寡占ではどうかという点について、リゲットは、「B&Wが、寡占市場において、他のシガレット会社との意識的平行行動(これだけでは違法とはいえない)によって無印品の価格を吊り上げ、競争水準を超える利潤を得ていた」と主張した(807) 。これに対して、最高裁は、「寡占価格による回収を狙った略奪価格差別を当然合法とした高裁判決に同意するわけには行かないし、また、B&Wが一定期間原価割れ販売をしていた証拠はあるが、市場の現実から見て、リゲットが主張するB&Wの反競争的行為を有責とするには根拠不十分である」(808) と判断した。最高裁がいう市場の現実とは、1)問題の期間中、無印シガレットの産出量がずっと増加していたことと、2)B&Wの市場シエアが12%にすぎなかったことである。いくら寡占でも、このような状態での価格吊り上げは不可能である。「反競争メヌエットは、習練を積んだ寡占者にとっても至難の芸である」(807) 。かくて、最高裁はB&W勝訴の地裁判決を確認した。
反対意見はスティヴンス判事の筆になるもので、大要、次のように言う。「1)B&Wがリゲットを目標にして価格戦争をしかけ、その手段として価格差別をおこなったこと、2)その投資を回収できるという期待を持っていたこと、および、3)B&Wの価格が平均変動費用を割っていたことはたしかである。実際には回収が成功しなかったとしても、リゲットを牽制して寡占体制に復帰させることに成功する蓋然性は高かった。長年メヌエットを踊ってきたプロのダンサーなら、ハイドンとモーツアルトの違いも分からない他人相手より、なじみのパートナーの動きを予測することははるかに容易だっただろう(816)
」。
第1部で見たように、略奪においては、投資局面と回収局面のそれぞれにおいて社会的非効率が発生するが、回収局面における単独または共謀による独占および価格差別は反トラスト諸法によって抑止される。それならば、投資局面の原価割れ販売も、それだけで(回収局面まで至らなくても)、なんらかの反トラスト法で規制すべきだというのが、伝統的な反トラスト思想であった。
これに対して、シカゴ学派は、投資だけを長期間にわたっておこなうというのは正気のビジネスとしては考えられない(したがって、この局面だけでの社会的非効率は、理論上は考えられるとしても、現実には存在しない)という現実認識にもとづいて、原価割れ販売だけを原因とする訴訟では、原告側の立証責任を加重することを提案し、これが最高裁に受け入れられたのである。
「不当廉売」といっても、「廉売」だけで不当なわけはない。それによって競争者が排除ないし牽制され、価格吊り上げによって投資が回収できるという危険なまでの蓋然性が立証されたときに、はじめて違法になるというのが、松下およびブラウン&ウイリアムソン両事件における最高裁の結論であった。
同じ略奪価格設定といっても、松下は共謀事件であり、ブラウン&ウイリアムソンは寡占市場における価格差別事件であった。あとは1社独占によるシャーマン法2条事件が出て、スタンダード石油判決が修正されれば、略奪事件の1世紀にちかい巨大な歴史のサイクルが閉じる(それとも、70年代の一連のIBM事件がそうだったのだろうか)。
地裁や州裁の抵抗にもかかわらず、松下からブラウン&ウイリアムソンへとまっすぐつながる最高裁の思想は揺るぎもない。その思想とは、自由競争こそ資本主義の本質だという信念である。70年にわたる社会主義との戦いに勝ちつつあった資本主義の自信がこの信念を支えている。
ここでいう競争とは、日本でよく聞く「公正競争」とか「競争秩序」というようなお行儀のよい中間概念ではない。競争は、相手を死に至らしめるまで止まらない、自然淘汰の戦いとしてとらえられている。「競争」はアナーキーな概念である。略奪は競争の極限の形態であり、両極端の間に善悪の便利な線など引けないのだというのが、シカゴ派経済学の苛烈な現実認識であった。
完全競争システムではどこにも超過利潤が蓄積されないから、システムそのものを否定するダイナミズムは、システム内部からは生まれない。完全競争システムは静的なニルヴァーナ(涅槃)である。そうではなくて、安売りと価格吊上げの「ゆらぎ」の中から社会的非効率と超過利潤が発生し、これが良かれ悪しかれ経済発展の原動力になるのだというひとつの歴史的仮説が、かかる現実認識から出発する。
1 エルジンガのこの着想は、略奪論のひとつの新しい方向を示しているようである。たしかに、米国やGATTのダンピング(異なる国家市場間の価格差別)防止規定が依拠するスタンダード石油判決程度の未熟な経済学はすでに超克されており、また、戦略貿易政策論者が好んで援用する日本のテレビ産業保護政策(Krugman, p. 169)に対する認識は、その方法論において、すでに松下判決によって完全に論破され、同じ方法論による半導体問題(Id. p. 91/Tyson)に対する認識も、今後の批判に耐えうるとは思えない。
一方、非価格略奪については、多製品間の費用移転による隠蔽工作とか、異常な設計変更や固定投資による技術戦略とか、略奪常習や低コストの評判をわざと立てることによって競争者を牽制する情報戦略とか、新規参入者にとってより苛酷な行政規制を陳情する政治戦略などなど、依然マッギーのいう「複雑珍奇な戦略行動モデル」が提案されている(Ordover & Wall, Wagle)が、いずれも、ほかにいくらでも有利な投資先がある成長分野の大企業が、本気で採用するにはあまりに矮小かつ非現実的なものになってきており、このような方向への略奪論は収穫が限界に近づいている。
2 1955年GATTに加盟した日本は、1964年貿易為替自由化大綱にしたがって急速に輸入自由化を進め、1963年GATT11条国移行時点で、非農産物については自由化率ほぼ100%に達し、また1964年IMF8条国移行にともない、経常支払や移転についての制限は完全に撤廃されていたので、法的な参入障壁は存在しなかった。したがって、原告は、その略奪論を、事実上の参入障壁としての'keiretsu'神話に依存させざるを得なくなったのである。
3 ここに記した1960年代の家電産業の状況は、当時、東京地区で家電営業に従事していた筆者の実見である。同じ産業現象に対して、別な描き方もある。小宮隆太郎、竹内宏、北原正夫、「日本の産業組織・・家庭電器」、中央公論、71年夏期特別号は慎重な留保を使いながらも、米国政府による日本製テレビ・ダンピング決定の背後に、日本メーカー間の共謀とそれによる超過利潤の蓄積、および日本市場における'keiretsu'参入障壁の存在を示唆したものだが、この論文は、本訴訟において、原告側主張を支持する強力な公開文献としてフルに利用された(後述)。
4 略式判決に先立って、地裁判事は、1)公開記録、2)日本語書証、3)鑑定人証言と題するいわゆる証拠意見書3部作によって、原告提出書証の大部分を不採用とした。やや細部にわたるきらいはあるが、とくに通商や産業に関する法律家と経済学者の事実認識方法の違いがよくあらわれているので、ここで触れてみたい。
まず、公開記録証拠意見書(Public Records Evidentiary Opinion, August 7, 1980, 505 F.Supp. 1125, reprinted in Appendix to Petition for a Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Third Circuit, June 7, 1984、以下本注での引用はAppendix版のページ番号)でまず問題になったのは、1921年反ダンピング法にもとづく財務省と関税委員会決定書の証拠能力である。地裁判事は、これらを、信憑性・関連性いずれもなしとして証拠不採用とした(713a ff)。主な理由は、1)これらの決定が証拠ヒアリングや反対尋問を経ていないこと(事実、79年までの反ダンピング関税は、輸入者側プロテストの結果、当初査定の80%もダウンしている)、および、2)比較が実勢価格ではなく人為的に構成された価額によるものであったことの2つである。
次に問題になったのは、1957年の公取委による対市場安定協議会勧告審決と、1966年開始の対テレビ6社審判の過程で審判官から公取委に対して提出された審決案の証拠能力である。地裁判事は、いずれについても、1)伝聞、2)信憑性なしとして証拠不採用とした。勧告審決は nolo plea(不抗争の答弁)に近いものとしてとらえられたのである。また、テレビ6社審判の「審決案」を、原告側は「Initial Decision」、被告側は「Draft of Decision」と訳し、それぞれ公取委による事実認定力の有無を争ったのだが、前者をワシントン大のヘイリー教授が、後者を上智大(当時)の松下満雄教授と元公正取引委員の有賀美智子女史が支持して証言した結果、地裁は後者を採用した(745a)。
つぎは日本語書証証拠意見書であるが、これは6社審判で公取委が押収したメーカー下級管理職の手帳類がほとんどで、地裁判事はすべて証拠不採用とした。原告が実質問題についてほとんどデポジションをとらなかった(厳密な直接証拠による審理ではなく、大量のプロパガンダで陪審勝訴を狙った)作戦が裏目に出たものといえよう。
最後は鑑定人証言証拠意見書(Expert Testimony Evidentiary Opinion, December 10, 1980, 505 F. Supp. 1313)である。これによって、原告側鑑定人報告書のほとんどが地裁で証拠不採用となり、高裁で一時息を吹き返したものの、最高裁が地裁の判断を再確認した(「『他に』証拠があれば審理しても良い」)ため、そのまま死文化したはずであるが、いまだに戦略貿易政策論など称する書物のなかに散見される(Krugman, p. 184)ので、ここでその概要と地裁の評価を記録しておくのが賢明であろう。
経済コンサルタントのディポドウィン氏は、大要、日本テレビ・メーカーが、米国メーカーを排除する目的で、本国より低い米国価格を設定する略奪共謀によって、米国で大きなマーケット・シェアをおさめたと結論する(1030a)。これに対して、地裁判事は、この意見書の根拠となった文献の大部分が、経済学者によって「合理的に依拠されるタイプの情報」(連邦証拠法 703条)ではないとし、また、この意見書は、「鑑定人が陪審の領域に侵入したものであって・・まさに共謀学宣誓屋のものであり・・原告弁護士の弁論に科学的信頼性の後光を添えたものにすぎない(1037a)」と酷評する。
ワシントン大学日本研究プログラム座長のヤマムラ教授(経済学)はディポドウィン氏と同工異曲の結論であるが、地裁判事は、これがディポドウィン意見書と同じ欠陥を有するばかりか、「原告側鑑定人意見書のなかで最も偏頗で(1079a)・・断定的かつ煽動的なレトリックに満ちており(1083a)・・もともと「・・と言われている」とか「・・と思われる」というような留保の多い小宮論文を5ページ半にわたってそのまま引用する等々・・ディポドウィン意見書より価値が低い(1086a)」と一蹴する。
5 First National Bank of Arizona v. Cities Service Co., 391 U.S. 253, 1951。1951年、イランのモサデグ政権がアングロ・イラニアン石油を国有化、これに対抗した国際メジャー6社がイラン石油の不買共謀をおこなったという容疑で、米国司法省が6社を提訴。一方、イラン石油の米国総代理人ウォルドロンが独立系のシティズ・サービスに売り込みをかけたが、ガルフがもっと安いクーエイト石油で対抗したためため破談。ウォルドロンは7社を共謀で訴えたが、シティズ・サービスは略式判決で勝訴。
6 原告は、米国の中小バイヤーが、「検査料」、「斡旋料」、「サービス費」などの支払いを日本から受け取っていたと主張し、法廷内外でこれをスキャンダラスに取り上げた。78年、米国財務省が、輸入者側情報提供不十分を理由に、「入手可能な最善情報」として物品税方式を採用したのも、これを契機としたものだった。
これら「リベート」の存在は、原告側の略奪論にとって不可欠の要素であった。というのは、チェック・プライス協定が高値輸出協定であることには議論の余地がなかったから、原告の略奪論が成立するためには、「リベート」によってチェック・プライス割れの安売りをするもうひとつの共謀が立証または推定される必要があったのである。
しかし、このようなリベートの存在を示す原告提出書証のどれひとつとして、法廷によって証拠採用されたものはなく、また、被告に反対尋問の機会が与えられたものもない。被告側を勝たせた地裁は、この問題に触れて、「リベート(が事実としても、それ)はむしろ米国への輸入に関して競争が存在したことの証拠のひとつ(513 F. Supp. 1154 (1981) )」(といっても被告勝訴の決定的要因ではなかったPonsolt & Lewyn, p. 608)としてとらえ、その事実の真否について判断していないか、ないしは否定的である(Id. 1307)。これは略式判決だから当然のことであるが、原告側主張だけが、いまだに文献のなかで独り歩きしている(Blair, Fesmire & Romano, p. 358)ので、あえてここで取り上げた。
7 Monsanto Co. v. Spray-Rite Service Corp., 465 U.S. 752, 1984 。除草剤の代理店スプレイ・ライトが安売りをして困るという訴外代理店の苦情を受けたメーカーのモンサントが、サービス能力不足等の理由でスプレイ・ライトの代理店更新に応じなかった(シャーマン法1条「縦の共謀」事件)。最高裁は、「単に訴外代理店の苦情によってスプレイ・ライトを切ったという状況証拠だけで原告の立証責任が満足される」とした下級審判決をしりぞけて、「共謀の推定には、モンサント独自の判断で代理店を切ったという可能性を排除する傾向を持つ証拠が必要」と判断しつつ、かかる証拠が存在するとして原告を勝たせた。
8 1916年法ダンピング問題。「ダンピングは価格差別の一形態で、1)二つの市場における価格弾力性が異なり、2)高価格市場(本国)で競争が制限されており、3)本国に参入障壁がある場合、ダンピング行為者にとって利潤を生じる。とくに、本国における需要の価格弾力性が低い場合、本国での利潤最大化価格は限界生産費よりかなり高いため、このマージンを利用したダンピングは必然のコースである」(William J. Baumol, THE LOGIC OF A DUMPING CONSIPIRACY THAT DAMAGES COMPETITION, A Report Submitted to the Court Attached to the Brief of Appellants on Remand, In Re Japanese Electronic Products Antitrust Litigation (3rd. Cir., June 16, 1986) 。
原告側鑑定人による上の記述から明らかなとおり、ダンピングは経済現象で、一般には「不公正」という要素はない。道徳的に非難されるべきダンピングがあるとすれば、それは、反競争的意図を持つ価格差別略奪の場合である(Areeda & Turner 1978, supra)。してみると、反ダンピング制度には、本来、1)独禁法の一部として、反競争的意図を持つ国際的な価格差別略奪を抑止するためのものと、2)通商法の一部として、国内産業を保護するためのものと、法の性格上、2種類あるのではないかという疑問が出てくる。この疑問に正面から答えたのが松下事件における1916年反ダンピング法略式判決である。
a)地裁略式判決 494 F. Supp.1199 (E.D.Pa. April 14, 1980)
いわゆる1916年反ダンピング法(15 U.S.C. §72)は、大要、次のように規定する:「ある物品を外国から合衆国へ輸入する者が、かかる物品(such articles)を、製造国内での実勢市場価額より低い価格で、合衆国内で販売することは違法である。ただし、かかる行為が、合衆国の産業を破壊する等の意図をもってなされた場合に限る」。
地裁判事の意見書は大要次のようである。「もともと、1916年反ダンピング法というのは、1914年発効のクレイトン法2条を補完するために制定されたものであって、反トラスト法の一部であり、国内産業保護法の1921年法(現1930年関税法731条以下)と違って、つねに競争促進的に解されなければならない。このことについては、原被告、法廷とも一致している」。
原被告双方の弁論は、輸出モデルに対応する国内モデルが何かという点に集中した。国内産業保護を目的とする1921年法では、これの判定について行政当局(財務省→商務省)に広い裁量が許されている。しかし、前述のように1916年法の解釈は1921年法とは違う。
地裁の結論は大要次のようである。「『かかる物品』の意味は、クレイトン法2条の『同等同質(of like grade and quality)』を基準として決定されなければならない。1916年法と違って、クレイトン法には判例が多数あり、『同等同質』とは、1)消費者の使用方法、2)消費者選好、3)商品性の一致を意味する。日米各市場向けテレビが、上の3点について一致しないことについては、原被告間に争いはない。米国で販売されたモデルと同等同質の日本向けモデルは存在しない。この点については、『重要な事実に関する真の争点』が存在しない。これは略式判決の要件を満たす。したがって、略式判決によって、原告請求を棄却する」。
b)高裁(第3巡回裁)判決 723 F. 2d 319 (3rd. Cir., December 5, 1983)
「比較対応モデルに関する地裁の判断基準には同意する。しかし、日米各市場向けテレビの電圧などが多少違っても、それぞれの市場での消費者効用が同じなら、ダンピング計算上は比較可能だ。原告は、かかる価格比較を鑑定人意見書の形で提出しているのだから、『重要な事実に関する真の争点』は存在する。したがって、地裁の略式判決は失当であり、これを差戻す」。
c)最高裁判決 475 U.S. 574, (March 26, 1986)
「被告側が略奪価格設定をおこなったという動機の立証が不十分である(ダンピングについても同断)。よって、高裁判決を差戻す」。
d)高裁(第3巡回裁)再判決 807 F. 2d 44 (3rd Cir., December 12, 1986)
最高裁の指示にしたがい、一審地裁略式判決を確認。これに対して、87年3月11日づけ原告側事件移送申立て理由書は、共謀(シャーマン法1条違反)容疑に関する主張を全面的に放棄、1916年反ダンピング法違反(個別および共謀)容疑一本に主張をしぼってきた。つまり、1916年反ダンピング法については、そもそも被告側から上告されていず、従って、最高裁判決によって差戻されてもいないのに、第3巡回裁がこの訴因まで棄却したのは越権行為だというのである。また、「被告側における略奪価格設定共謀の動機不存在が、同時にダンピングの動機不存在を意味する」という第3巡回裁の判断に対しても、原告は、「略奪価格設定とダンピングでは経済的動機が違う点について、第3巡回裁は審理不尽だ」と主張。しかし、前述のとおり、87年4月24日、最高裁がこれを却下、被告側勝訴が確定した。
9 政府強制問題。松下事件は、表面的には、主として1)違法推定における証拠問題、従として2)ダンピング私的救済問題として、もっぱら私法問題として推移したのであるが、実は、その底には「一国の裁判所が他国の通商政策を裁くことができるか?」という重大な公法問題をはらんでいたのである。地裁、高裁、最高裁とも、この問題を十分意識していながら、それをあえて避けて、私法的表面だけで裁判したというのが真相のように思われる。そもそも、原告側最大の直接証拠というのは、1963年から73年まで、それぞれ、輸取法5条3および同11条にもとずいて存在した、いわゆるメーカー協定と輸組規約であった。これらは、あわせて「チェックプライス協定」と呼ばれ、主として対米輸出テレビ各インチサイズごとに最低輸出価格を定めており、前者は、テレビ全メーカーがメンバーとなっていた。とくに後者には、米国内輸入業者の登録を定めたいわゆる5社枠というものがあって、裁判の過程で大きな問題になった。原告主張では、チェックプライス協定は価格協定、5社枠は顧客分割で、ともにシャーマン法1条のper se illegalである。かかる主張に対して、日本政府は、これらの協定が政府によって強制されたものだ(したがって、主権強制にあたり、違法性を阻却する)という声明をおこなった。これがいわゆるMITIステートメントである。
原告は、その鑑定人意見書(Haley)のなかで、輸取法を根拠法とするチェックプライス協定が加入脱退自由であり、また、通産省の承認や届出に先だって競争者間の協定が存在するから主権強制に該当しないという立場をとった。これに対し、MITIステートメントは、「秩序ある輸出を確保するため、通産省は法律に基づく2つの基本的手続きを発達させてきた。その第1は輸取法で、第2は外為法である。(輸出秩序確保のために)何らかの措置が必要とみられる場合、通産省は、まず、当該業界に対して、輸取法に基づく取極めを結ぶことを指示する。・・目的達成のために上の手続きが不十分とみられる場合、通産省は、業界に対して、直接、外為法に基づく輸出貿管令による権限を行使する」・・として、輸取法にもとづくチェックプライス協定も、実際は、法律による強制力の裏づけを持っていたことを言明した。
MITIステートメントは、はじめ、75年4月25日づけ在米日本大使館発ディプロマチック・ノートの添付文書として米国国務省経由フィラデルフィア連邦地裁に届けられたが、これは手続き的に不満だったので、80年7月11日づけ在米日本大使館発連邦地裁判事あてアミカス・キュリエ・ブリーフ(法廷助言書)が、「通産省が、日本政府の基本的通商政策細目を実行する権限と責任を有し、かつ、日本政府を代表して、当該ステートメントを発する権限を有する」旨の証明・確認をおこなっている。問題は、かかる一国政府の正式ステートメントの内容の真否を、米国の陪審員が審理できるかどうかである。
81年3月27日、フィラデルフィア連邦地裁の略式判決は、主権強制免責に関する原被告の主張を詳細に記述しつつも結論を避け、略式判決における状況証拠の問題にしぼって判決した。
83年12月5日、第3巡回裁の差戻し判決は、MITIステートメントを全く無視したばかりか、問題の通産省指示が主権強制にあたるかどうかは、事実審において陪審員が決定すると述べている。これに対し、日本被告側は、最高裁あて事件移送命令の申立てにおいて、「ある輸出手続が一国政府によって強制されたことを証言する同国政府の正式声明を、高裁が無視したり、その内容の真否を陪審員に審理させることは合法か?」という趣旨の問題提起をおこなった。
被告側の事件移送命令申立てにもとずく最高裁の審理中、各国政府(日米英加豪仏韓)から法廷助言書がよせられたが、このうち、とくに充実した内容を持つ米国司法省のそれ(85年6月17日づけ)は、まず、「国家間および連邦政府3権間の礼譲が、外国主権行為の効力についての紛争に対する司法権の不介入を原則とする国家行為理論を作り出した」との認識に立ち、「国家行為理論に基づく防御は独禁法の法文や制定経緯の中に明記されているわけではないが、議会によるシャーマン法制定の背景となった『法的文脈』の主要部分として共通に認識されており、したがってシャーマン法固有の防御手段となっている」と結論する。また、英加豪仏4国政府共同の法廷助言書(85年6月15日づけ)は、より直截に、「自国領土内における主権者の行為が他国の裁判所の審理の対象とならないことは、国際法の基本原則である」と述べている。
86年3月26日づけ最高裁判決は、本件差戻しのためには、原告被害不存在という理由だけで十分だから、国家強制の問題には触れないと述べるにとどまり(475
U.S. 574. 1348, 559)、上の問題提起(「外国政府の正式声明は、裁判上、直ちに、真実の証拠として採用され、その内容の真偽は審理の対象にならないか?」)には直接には答えていない。
Areeda, Philip & Donald F. Turner, PREDATORY PRICING AND RELATED PRACTICES UNDER SECTION 2 OF THE SHERMAN ACT, 88 Harv. L. Rev. 697 (1975).
Areeda, Philip & Louis Kaplow, ANTITRUST ANALYSIS (Little Brown, Boston, MA. 1988).
Austin, Page I., PREDATORY PRICING LAW SINCE MATSUSHITA, 58 Antitrust L. J. 895 (1989). ○
Benz, Steven F., BELOW-COST SALES AND THE BUYING OF MARKET SHARE, 42 Stan. L. Rev. 695 (1990). ●
Blair, Roger D., James M. Fesmire & Richard E. Romano, AN ECONOMIC ANALYSISOF MATSUSHITA, 36 Antitrust Bull. 355 (1991). ○
Bork, Robert H., ANTITRUST PARADOX: A POLICY AT WAR WITH ITSELF (Basic Books, N.Y. 1978).
Brodley, Joseph S. & George A. Hay, PREDATORY PRICING: COMPETING ECONOMIC THEORIES AND THE EVOLUTION OF LEGAL STANDARDS, 66 Cornell L. Rev. 738 (1981).
Cox, David J., MATSUSHITA V. ZENITH 18 Cap. U. L. Rev. 141 (1989). ●
Creighton, Joseph R., MATSUSHITA V. ZENITH REVISITED. 15 Int'l Bus. Law 247 (1987). ●
Crew, Eugene, MATSUSHITA V. ZENITH: THE CHICAGO SCHOOL TEACHES THE SUPREME COURT A DUBIOUS LESSON, 1 Antitrust 11 (1986). ●
DeSanti, Susan S. & William A. Kovacic, MATSUSHITA: ITS CONSTRUCTION AND APPLICATION BY THE LOWER COURTS, 59 Antitrust L. J. 609 (1990). ○
Easterbrook, Frank H., PREDDTORY STRATEGIES AND COUNTERSTRATEGIES, 48 U. Chi. L. Rev. 263 (1981).
Elzinga, Kenneth G., THE NEW INTERNATIONAL ECONOMICS APPLIED: JAPANESE TELEVISIONS AND U.S. CONSUMERS, 64 Chi.-Kent L. Rev. 941 (1988). ◎
Fisher, Franklin M., MATSUSHITA: MYTH V. ANALYSIS IN THE ECONOMICS OF PREDATION, 64 Chi.-Kent L. Rev. 969 (1988). ◎
Ganjaei, Ali, MATSUSHITA V. ZENITH, 15 Denv. J. Int'l L. Pol'y 395 (1988). ○
Griffin, Joseph P., MATSUSHITA V. ZENITH REVISITED AGAIN: A REPLY TO MR. CREIGHTON, 15 Int'l Bus. Law 294 (1987). ◎
Hirshleifer, Jack, PRICE THEORY AND APPLICATIONS, 2ND ED. (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1980).
Krugman, Paul R., ed., STRATEGIC TRADE POLICY AND THE NEW INTENATIONAL ECONOMICS (The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1986).
Jorde, Thomas M. & Mark A. Lemley, SUMMARY JUDGMENT IN ANTITIRUST CASES: UNDERSTANDING MONSANTO AND MATSUSHITA, 36 Antitrust Bull. 271 (1991). ◎
Leigh, Monroe, ANTITRUST - HIGH STANDARD OF PROOF REQUIRED TO SHOW EXISTANCE OF CONSPIRACY, 80 Am. J. Int'l L. (1986). ○
Levine, Brenda S., PREDATORY PRICING CONSPIRACIES AFTER MATSUSHITA V. ZENITH, 22 Int'l L. 529 (1988). ●
Liebeler, Wesley J., WHITHER PREDATORY PRICING? FROM AREEDA AND TURNER TO MATSUSHITA, 61 Notre Dame L. Rev. 1052 (1986). ◎
McArthur, John B. & Thomas W. Patterson, THE EFFECTS OF MONSANTO, MATSUSHITA AND SHARP ON THE PLAINTIFF'S INCENTIVE TO SUE, 23 Conn. L. Rev. 333 (1991). ●
McGee, John S., PREDATORY PRICE CUTTING: THE STANDARD OIL (N.J.) CASE, 1 J. L.& Econ. 137 (1958).
McGee, John S., PREDATORY PRICING REVISITED, 23 J. L. & Econ. 289 (1980).
Ordover, Janusz A & Daniel M. Wall, PROVING PREDATION AFTER MATSUSHITA: WHAT THE "NEW LEARNING" HAS TO OFFER, 1 Antitrust 5 (1987). ◎
Ponsoldt, James F. & Marc J. Lewyn, JUDICAIL ACTIVISM: THE ILLOGIC OF MATSUSHITA, 33 Antitrust Bull. 575 (1988). ●
Posner, Richard A., ANTITRUST LAW--AN ECONOMIC PERSPECTIVE, (The University of Chicago Press, Chicago, Ill., 1976).
Sherman, Randolph, THE MATSUSHITA CASE: TIGHTENED CONCEPTS OF CONSPIRACY AND PREDATION? 8 Cardozo L. Rev. 1121 (1987). ●
Sievers, Mark & Brooks Albery, STRATEGIC ALLOCATION OF OVERHEAD, 60 AntitrustL. J. (1991). ○
Simkovic, Martin S., JUDICAIL TESTS TO DETERMINE PREDATORY PRICING BEFORE AND AFTER MATSUSHITA, 44 U. Miami L. Rev. 839 (1990). ●
Soma, John T. & Andrew P. McCallin, SUMMARY JUDGMENT AND DISCOVERY STRATEGIESIN
ANTITRUST AND RICO ACTIONS, 36 Antitrust Bull. 325 (1991). ○
Tyson, Laura D'Andrea, WHO'S BASHING WHOM: TRADE CONFLICT IN HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIES (Institute for International Economics, Washington, D.C. 1992).
Wagle, M. Steven, PREDATORY PRICING, A CASE STUDY: MATSUSHITA V. ZENITH, 22 Creighton L. Rev. 89 (1988). ◎
Yu, Esmeralda D., ANTITRUST LAW: THE NADIR OF THE PREDATORY PRICING THEORY? 10 Harv. J. L. & Pub. Pol'y 243 (1987). ●